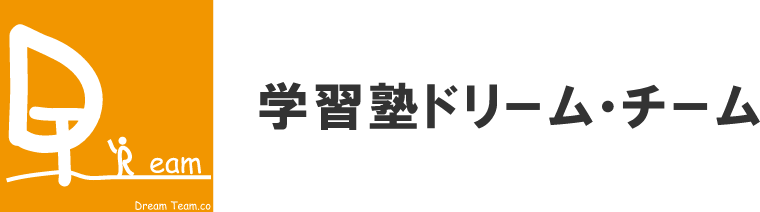

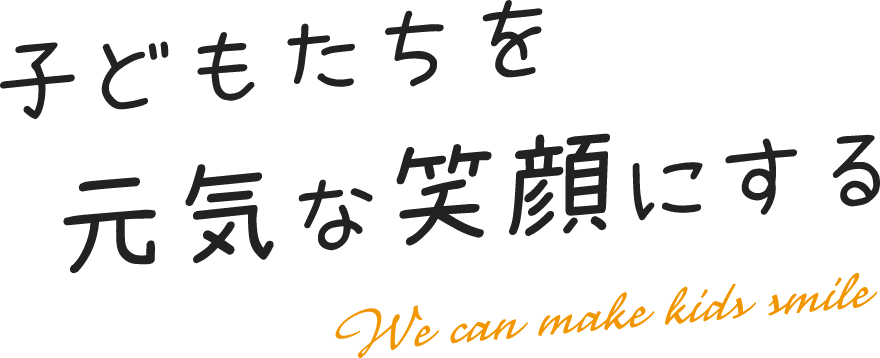
受付時間 10:00~22:00
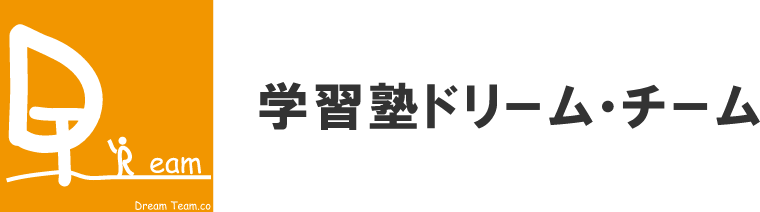

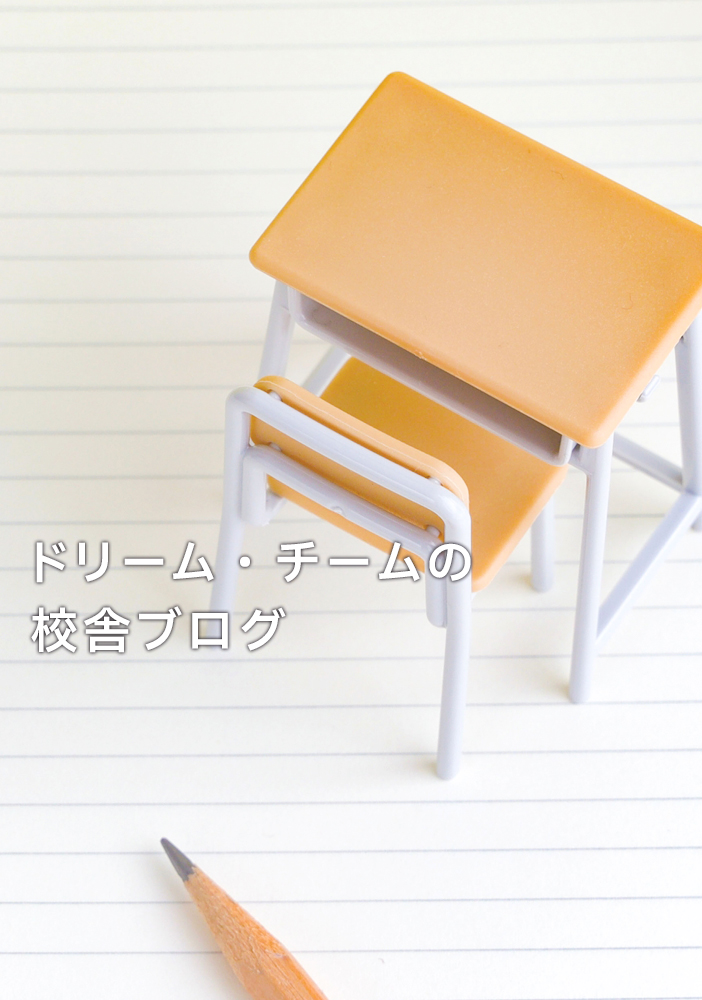
2025年02月07日
福岡市城南区の個別指導学習塾ドリーム・チーム城南ゼミナールです。
いろいろな塾で、大なり小なり、生徒さんが守るべき何らかのルールを設定されていると思います。
比較的厳しくルールを設定して厳格に運営するスタンスもあれば、意図的にゆるくしている塾さんもいらっしゃると思います。
どんなルールを、どのくらいの量、どのくらいの「強制力」を持って運営するかは、塾のブランドや塾長の方針・教育観などにもよってきますので、それぞれに判断が分かれるところです。
もちろん、何が正しいとか間違っているとかいう問題でもありません。
ただ「ルール」の存在や内容について、子どもたちや学校がどう捉えているか、現代社会のトレンドを抑えておくことは役に立つと思います。
では、世の中的にはどうなのでしょうか?
ある記事の内容をざっくりとレジュメ的にまとめます。
・校長と生活指導担当の先生方に、アンケートを実施
・関東7都県にある高校のうち、校則の見直しについて8割超が「必要」と考えている
・実際に校則見直しを「実施している」「予定している」学校も8割以上
・生徒指導提要の改訂が強く影響していると思われる
一つ目のポイントは、子どもたち自身ではなく先生方(学校)も「校則を変えたほうが良い」と思っていることだと感じました。
下着の色の指定や、地毛が茶色系なのに黒く髪を染めさせるなど、人権侵害にも近い “ブラック校則”が社会問題にもなりましたが、やはり先生方も客観的に考えて「それはおかしい」と思われているのでしょうね。
ちなみに、見直すべき校則で上位に入ったのは「制服のジェンダーレス化」、「制服の夏服冬服切り替え時期の柔軟化」、「登下校時の服装」、「スマホや携帯の使用に関すること」だそう。
傾向として共通して言えそうなのは、ルールで縛って押し付けるのではなく、「生徒自身の主体性や判断に委ねる」要素が強いことではないでしょうか。
これが一般化していけば、現代の子どもたちの「ルール観」もおそらくそのように変わっていきます。
つまり、かつての強権的な学校(先生や校則)のイメージは弱まっていくことが予想されるわけですが、これが塾にも影響するかもしれません。
あまりに強引だったり、極端だったり、時代錯誤が過ぎたりするようなルール設定を続けていると、
「学校と違って、塾は強制的にルールを押し付けてくる」
「学校と違って、塾の先生は生徒を信用してくれない(からルールで縛る)」
と思われてしまうかも……
とは言え逆に「学校が“ゆるい”から、塾では厳しくしてもらったほうが勉強に集中できていい」と感じる生徒さんもいると思います。
ある程度、強制力があったほうが動きやすいタイプの子どもたちですね。
もう一つのポイントは、「生徒指導提要の改定の影響」という部分です。
生徒指導提要とは、生徒指導における基本的な考え方や価値観、方法論などを示したガイドブックのようなもの。
平成22年に始めて作成され、令和4年に改訂がなされました。
改定の要諦はいくつかあるのですが、留意したいのは「児童生徒の権利の理解」という項目が新設されたことです。
生徒指導を実践する上で、子どもの権利条約の一般原則に沿って「差別の禁止」「子どもの最善の利益の保障」「生命・生存・発達への権利」「意見表明権」への理解が不可欠とされました。
つまり、校則や学校での生徒指導は、これらが根底になければいけないということです。
もっと言えば、そもそも「子どもの権利条約」は世界条約ですので、校則とか学校とか関係なく、子どもであるというだけで保障されるべき権利なわけです。
注意したいのは「子どもの最善の利益の保障」「意見表明権」あたりでしょうか。
そのルールは、真に子どもたちの利益に適うものか(=塾の都合を押し付けていないか)、子どもたちに意見を述べる機会を与えた上で作ったものか、を客観的に見直してみる必要があると思います。
特に「意見表明権」については、そのような権利を子どもが有していることすら知らない大人が多いことが大きな問題になっているそうです。
「つべこべ文句を言うな、黙って従え」は不適切であるというのが、現代社会の価値観だと考えておきましょう。


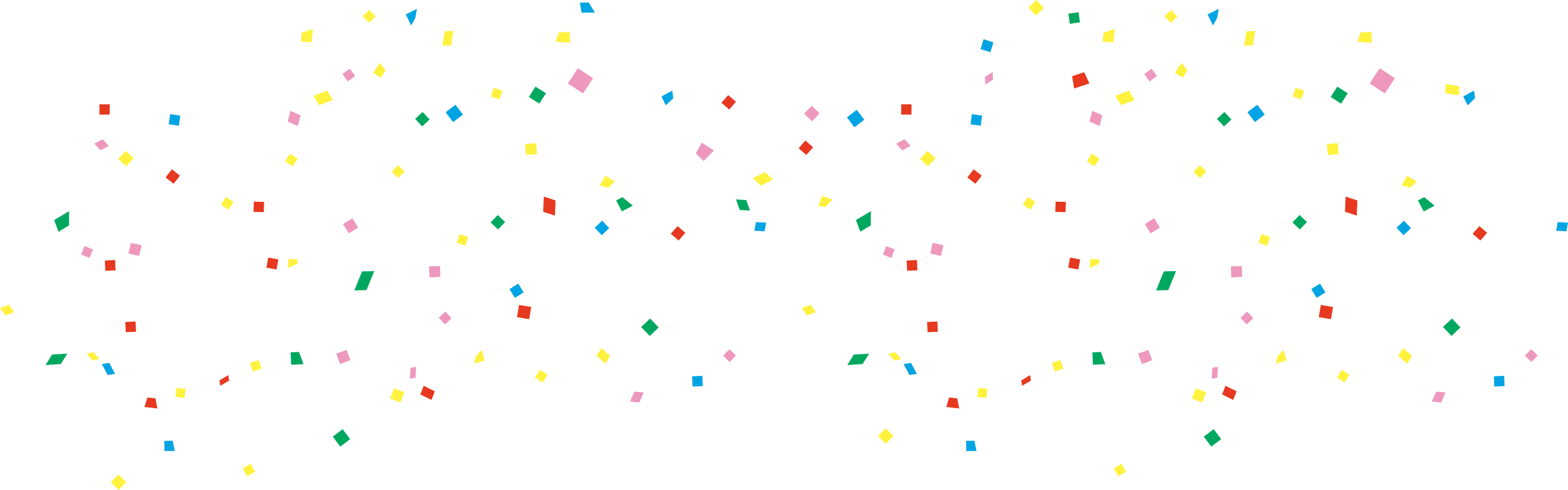
お子様の学習状況をヒアリングしながら、ご説明します。
ご不明な点や、気になるところもお気軽にご相談ください。
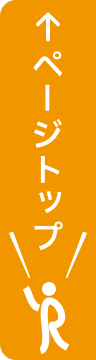
Dreamteam Co.,Ltd. All Right Reserved.